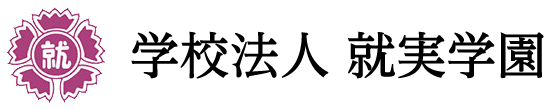就実学園からのお知らせ
News
就実学園からのお知らせ
News
- TOP
- 就実学園からのお知らせ
就実小学校の授業に学生も参加 サポートとともに交流も深めました
就実小学校の授業に学生も参加 サポートとともに交流も深めました
学生の研究や学修の成果を児童の学びにも活かしてもらおうと、就実小学校の授業に、就実大学・就実短期大学の学生が参加してサポートにあたるとともに、交流も深めました。
このうち2025年2月13日(木)には、短大生活実践科学科の2年生2人が、久保美沙登 准教授とともに、全学年でつくる「縦割り探求」グループのひとつに参加しました。
グループでは、この1年、環境をテーマに活動してきました。この日は、廃材を活用したアート作品づくりで、古新聞のドレスに色紙を折った花やリボンを飾り付けたり、廃棄ダンボールから作ったツリーに、葉や手形をかたどった和紙を貼るなどして、作品に仕上げていきました。
学生たちは、大学で、紙を材料にドレスなどをデザインするペーパーファッションに取り組んでおり、廃棄物に新たな価値を付けて再生するアップサイクルも学修しています。
児童との活動では、色紙の折り方を手ほどきしたり、より見栄えのする飾り方や貼り方をアドバイスするなど、児童の創造性を尊重しながらサポートにあたりました。

また2月15日(土)には、就実小・授業研究発表会の公開授業(4年A組社会科(小寺祐輔 先生))に、経営学科の3年生5人が参加しました。
児童は、森林資源やジビエを積極的に活用する岡山県西粟倉村を例に、特色ある地域について学んでいて、この日は、学習のまとめとして、村の魅力を伝える写真4枚を選び、組み合わせる課題に取り組みました。
学生たちは、去年、地域おこしの政策アイデアを競う全国大会で受賞したチームのメンバーで、“実績”を買われ、この授業でのサポートを依頼されたということです。
授業では、班ごとにひとりずつが加わり、写真を選ぶポイントを伝えたほか、まとめを発表する児童に「がんばって!」と声をかけるなど、交流も深めました。

参加した学生たちは、みな初めて就実小を訪れたということです。授業後は、「児童の豊かな発想力に驚いた」「タブレットやアプリを使いこなす姿に感心した」などと感想を話すとともに、児童との触れ合いを楽しく振り返っていました。